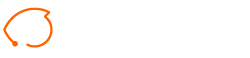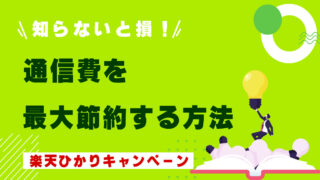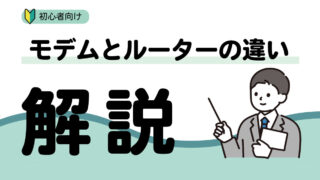- 2025年7月11日
Wi-Fiが夜繋がらない!原因と解決策を徹底解説【2025年5月最新版】
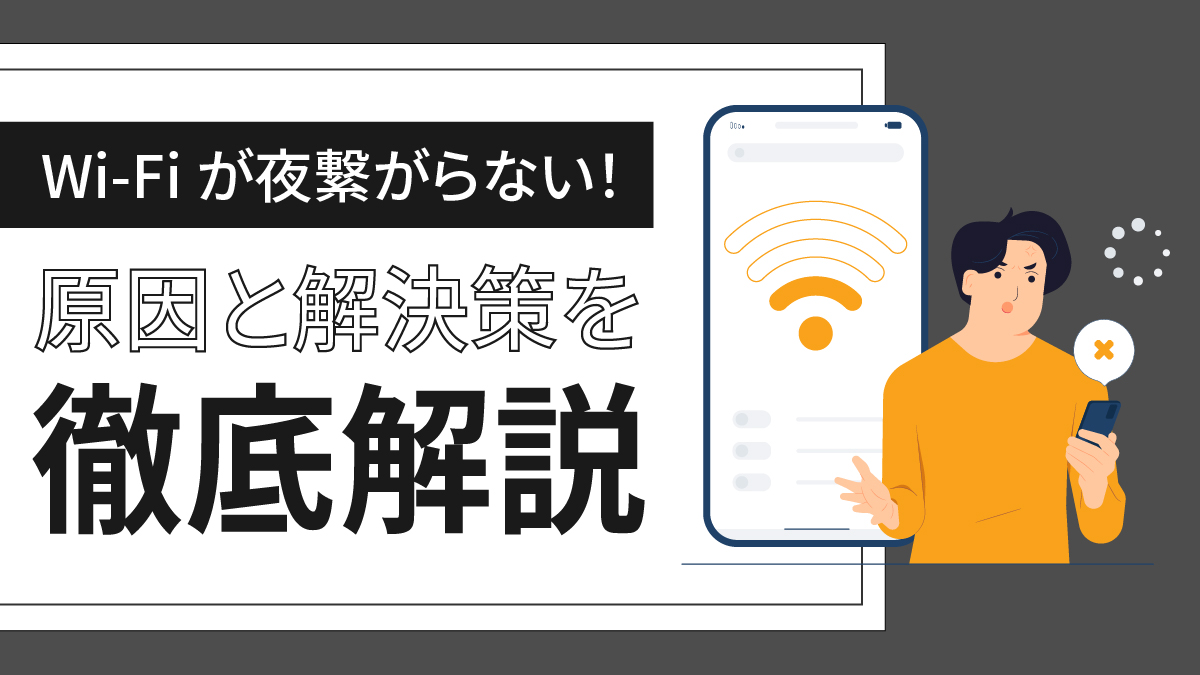
夜になるとWi-Fiが繋がりにくくなることはありませんか?本記事では、その原因と効果的な解決策を紹介します。
夜だけWi-Fiが繋がらない現象について
「夜になるとWi-Fiの調子が悪くなる」という現象は多くの人が経験しているのではないでしょうか。日中は快適に使えていたインターネットが夕方から夜にかけて突然遅くなったり、頻繁に切断されたりする状況に悩まされている方は少なくありません。
総務省の「インターネット利用環境の実態調査」によると、特に19時から23時の時間帯にインターネット速度の低下を経験するユーザーが最も多いことが報告されています。ではなぜこのような現象が起きるのでしょうか。
夜間にWi-Fi接続トラブルが増加する理由
夜間にWi-Fi接続トラブルが増加する主な理由は、同時接続ユーザー数の急増にあります。多くの人が仕事や学校から帰宅し、同じような時間帯にインターネットを利用し始めることでネットワークに大きな負荷がかかります。
特に、平日の20時から22時にかけては動画視聴やオンラインゲーム、SNSの利用が集中する「ゴールデンタイム」となり、回線の混雑が顕著になります。このような時間帯には同じエリア内で多くのユーザーが同時に大容量のデータをやり取りするため、回線の帯域が圧迫されます。
日本インターネットプロバイダー協会の調査によれば、平均的な家庭では夜間のインターネットトラフィックが日中の約2.5倍に増加するというデータもあります。
| 時間帯 | トラフィック量(相対値) | 接続トラブル報告数 |
|---|---|---|
| 午前(6時〜12時) | 1.0(基準値) | 少 |
| 午後(12時〜18時) | 1.3〜1.5 | 中 |
| 夜間(18時〜24時) | 2.0〜2.8 | 多 |
| 深夜(0時〜6時) | 0.5〜0.8 | 少 |
また、マンションやアパートなど住宅が密集している地域では、近隣のWi-Fi機器からの電波干渉も原因のひとつとなります。特に夜間は多くの世帯でWi-Fi機器が同時に稼働するため、電波干渉のリスクが高まります。
時間帯によるWi-Fi接続品質の変化とは
Wi-Fiの接続品質は一日の中でも時間帯によって大きく変動します。これはネットワークの混雑度だけでなく、さまざまな要因が複合的に影響しています。
朝の時間帯(7時〜9時)は、多くの人が出勤・登校前にスマートフォンや各デバイスでニュースやSNSなどをチェックするため、一時的に接続品質が低下することがあります。日中(10時〜16時)は比較的安定していますが、夕方から夜(18時〜23時)にかけて急激に品質が低下するのが一般的なパターンです。
夜間のWi-Fi接続品質は、速度低下、頻繁な接続切れ、ウェブページの読み込み遅延、動画のバッファリング、オンラインゲームの遅延(ラグ)などの形で現れます。これらの症状は特定のデバイスだけでなく、家庭内のすべての機器に影響することが多い点が特徴です。
JPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)の資料によると、インターネットの一般的な利用パターンは次のように分類されます。
- 朝 :ニュースやメールの確認が中心
- 日中:ビジネス利用やテレワークが中心
- 夜 :動画視聴、オンラインゲーム、SNSが中心
特に夜の利用は大容量のデータ転送を必要とするアプリケーションの使用が増えるため、帯域を大きく消費します。たとえば、高画質の動画ストリーミングサービスは約5〜7Mbpsの帯域を、4K動画では約25Mbpsを必要とします。複数の家族が同時にこうしたサービスを利用すると、家庭内のネットワークにも大きな負荷がかかります。
また、NICTの日本のインターネットトラフィック観測によれば、週末と平日では利用パターンが異なり、週末は一日を通じてトラフィックが高めに推移する傾向があります。これは家族全員が在宅していることによる影響だと考えられます。
時間帯による接続品質の変化を理解することで、問題が発生しやすい時間帯を予測し、適切な対策を講じることができます。ここからは、こうした夜間のWi-Fi接続問題の具体的な原因について解説します。
Wi-Fiが夜に繋がらなくなる一般的な原因
夜になるとWi-Fiが繋がりにくくなったり、速度が低下したりする現象は多くの方が経験したことがあると思います。ここでは、なぜ夜間のWi-Fi接続に問題が生じるのか、その一般的な原因を解説します。
回線の混雑と帯域制限
夜間のWi-Fi接続問題で最も一般的な原因は回線の混雑です。特に、18時から23時頃までのいわゆる「ゴールデンタイム」には多くの利用者が同時にインターネットを使用します。
同じ地域内で多くの人が同時にネットを使うことで通信回線に大きな負荷がかかり、結果として接続速度の低下を引き起こします。これは、特に集合住宅や人口密集地域で顕著に表れる現象です。
総務省の「我が国のインターネットにおけるトラヒックの集計結果」によると、平日夜間のインターネットトラフィックは日中の約1.5〜2倍に達することがあるようです。
| 時間帯 | 混雑状況 | 速度低下の一般的な程度 |
|---|---|---|
| 日中(10:00-17:00) | 比較的空いている | ほぼなし〜20%程度 |
| 夕方(17:00-19:00) | 混雑し始める | 20%〜40%程度 |
| 夜間(19:00-24:00) | 最も混雑する | 30%〜70%程度 |
| 深夜(0:00-6:00) | 空いている | ほぼなし |
また、一部のインターネットサービスプロバイダー(ISP)では、特に混雑する時間帯に「帯域制限」を実施していることがあります。これは、大量のデータをダウンロードしたりストリーミングしたりする特定のユーザーの通信速度を意図的に制限することで、他のユーザーの接続品質を保つための措置です。
電波干渉の増加
夜間には電波干渉の問題も増加します。Wi-Fiルーターは特定の周波数帯を使用して通信しますが、同じ周波数帯を使用する機器が増えると干渉が発生し通信品質が低下します。つまり、集合住宅では夜間に多くの世帯が同時にWi-Fiを使用するため、近隣のWi-Fiルーターとの電波干渉が発生しやすくなります。これは特に一般的な2.4GHz帯で顕著に表れる問題です。
電波干渉の発生源となる一般的な機器には以下のようなものがあります。
- 近隣のWi-Fiルーター(特に同じチャンネルを使用している場合)
- Bluetoothデバイス(ワイヤレスヘッドホン、スピーカーなど)
- 電子レンジ(特に2.4GHz帯に干渉)
- コードレス電話
- ベビーモニター
- 無線防犯カメラ
夜間はこれらの機器の使用頻度が高まるため、Wi-Fi接続に問題が生じやすくなります。
| 周波数帯 | 特徴 | 干渉の影響 |
|---|---|---|
| 2.4GHz | 障害物に強く、範囲が広い | 干渉を受けやすく、夜間の接続問題が発生しやすい |
| 5GHz | 高速だが障害物に弱い | 比較的干渉が少ないが、範囲が限られる |
機器の過熱問題
Wi-Fi機器の長時間使用による過熱も、接続問題の原因の一つです。一日中稼働しているルーターは、特に夏場や通気性の悪い場所に設置されている場合、夜に内部温度が上昇していることがあります。
多くのルーターには過熱保護機能が搭載されており、一定温度を超えると自動的にパフォーマンスを下げることで機器を保護します。これにより、結果的に通信速度が低下したり接続が不安定になったりすることがあります。
ルーターの過熱は以下のような状況で特に発生しやすくなります。
- 換気の悪い場所(棚の中や家具の後ろ)に設置されている場合
- ホコリが蓄積している場合
- 他の熱を発する機器(テレビ、ゲーム機など)の近くに置かれている場合
- 長時間にわたって大量のデータを転送している場合(動画ストリーミング、大型ゲームのダウンロードなど)
日本家電製品協会の調査によれば、適切な通気が確保されていないルーターは連続使用時に内部温度が外気温より15℃以上高くなることがあるようです。
ISP側のメンテナンスと負荷
インターネットサービスプロバイダー(ISP)側の要因も夜間のWi-Fi接続問題に関係しています。多くのISPは、ユーザーへの影響を最小限に抑えるため定期メンテナンスを夜間(特に深夜)に実施することがあります。
メンテナンス中は一時的な接続切断や速度低下があったり、また、メンテナンス情報が事前に通知されていない場合は、接続問題が突然現れれたりすることもあります。
さらに、ISPの設備自体が夜間の高トラフィックに対応しきれていないケースもあります。特に以下のような状況では、ISP側の負荷が原因で夜間の接続品質が低下することがあります。
- 急激な契約者数の増加に設備の増強が追いついていない地域
- 人口密集地域における集中的なネットワーク利用
- 大型アップデートや人気コンテンツのリリースによる一時的な過負荷
たとえば、人気ゲームの大型アップデートが配信されるタイミングや、話題の配信コンテンツが公開される際には、多くのユーザーが同時にダウンロードやストリーミングを行うため通常以上の負荷がかかることがあります。
これらの要因が複合的に作用し、Wi-Fi接続が不安定になる現象が引き起こされます。ここからは、こうした問題を解決するための具体的な対策を紹介します。
Wi-Fiの接続問題を解決する基本対策
ここでは、専門知識がなくてもWi-Fiの接続問題を解決するために実践できる基本的な方法を紹介します。特別な道具や技術を必要としない方法がほとんどなので、ぜひ試してみてください。
ルーターの再起動
最も簡単かつ効果的な対策は、Wi-Fiルーターの再起動です。この方法は「電源の入れ直し」とも呼ばれ、IT業界では「Have you tried turning it off and on again?(電源を切って、入れ直してみましたか?)」という有名なフレーズがあるほど基本的な解決策です。
ルーターの再起動によって一時的なメモリーの不具合やプロセスの停滞がリセットされ、正常な状態に戻ることがあります。特に長時間連続稼働しているルーターには効果的な方法です。
再起動の手順は以下のとおりです。
- ルーターの電源ケーブルを抜く
- 最低30秒間待つ(内部のコンデンサの放電のため)
- 電源ケーブルを再接続する
- ルーターが完全に起動するまで1〜3分待つ
総務省の「ICTサービス安心・安全研究会」の報告によると、単純な再起動で約40%のネットワーク接続問題が解決するというデータがあります。
また、定期的に再起動をスケジューリングすることも有効です。多くの最新ルーターでは、深夜など指定した時間に自動再起動する機能が搭載されています。
Wi-Fiチャンネルの最適化設定
夜間にWi-Fi接続が悪化する主な原因の一つは、近隣のWi-Fiネットワークとのチャンネル干渉です。特にマンションやアパートなどの集合住宅では、この問題が顕著になります。
Wi-Fiは特定のチャンネル(周波数帯)を使用して通信しますが、同じチャンネルを使用するネットワークが近くに多いと互いに干渉し、接続品質が低下します。夜間は多くの人がインターネットを利用するため、チャンネル干渉が日中より増加します。
最適なチャンネルを設定する方法と手順を紹介します。
- スマートフォンに「Wi-Fi Analyzer」(Android)や「Network Analyzer」(iOS)などのアプリをインストールする
- アプリを使って周辺のWi-Fiネットワークが使用しているチャンネルを確認する
- 使用頻度の低いチャンネルを特定する
- ルーターの管理画面にアクセスし、Wi-Fi設定でチャンネルを手動設定する
2.4GHz帯でよく使われるチャンネルは1、6、11です。これらのチャンネルは互いに干渉しにくいという特徴があります。
| 周波数帯 | 推奨チャンネル | 特徴 |
|---|---|---|
| 2.4GHz | 1, 6, 11 | 互いに干渉しにくい |
| 5GHz | 36, 40, 44, 48など | チャンネル数が多く、干渉が少ない |
多くの最新ルーターには「自動チャンネル選択」機能がありますが、この機能が必ずしも最適なチャンネルを自動で選択するとは限りません。手動設定の方が効果的な場合も多いため、万が一のときはこの方法を試してみてください。
5GHzと2.4GHz帯の使い分け
現代のWi-Fiルーターのほとんどは、2.4GHzと5GHzの両方の周波数帯をサポートしています。周波数帯にはそれぞれ特徴があり、状況に応じて使い分けることで夜間の接続問題を軽減できます。
5GHz帯は2.4GHz帯に比べてチャンネル数が多く、干渉が少ないため、夜間の混雑時に特に有効です。一方で、壁や床などの障害物を通過する能力は2.4GHz帯の方が優れています。
| 項目 | 2.4GHz帯 | 5GHz帯 |
|---|---|---|
| 通信速度 | 比較的遅い | 速い |
| 障害物への強さ | 強い(壁を通過しやすい) | 弱い(直線的に届きやすい) |
| 干渉の可能性 | 高い(電子レンジなども使用) | 低い |
| 混雑状況 | 混雑しやすい | 比較的空いている |
| 適した用途 | 広範囲をカバー、IoT機器 | 高速通信、動画視聴、ゲーム |
周波数帯の使い分け方法を紹介します。
- 動画ストリーミングやオンラインゲームなど、高速通信が必要なデバイスは5GHz帯に接続する
- スマートホーム機器やルーターから離れた場所にあるデバイスは2.4GHz帯に接続する
- ルーターの設定で各周波数帯のSSID(ネットワーク名)を分けて管理する
ルーターの設置場所の見直し
Wi-Fiの接続品質はルーターの設置場所にも大きく左右されます。理想的なルーターの設置場所は、家の中心付近で、高さがある場所、かつ障害物が少ない場所です。金属製の物体、水槽、電子レンジ、Bluetoothデバイスなどは電波を妨げる可能性があるため、設置の際はこれらの近くには置かないよう注意しましょう。
ルーターの設置場所を見直す際のポイントを以下にまとめます。
- 床から1m以上の高さに設置する(電波は上下より横に広がりやすい)
- 金属製の家具や電化製品から離す
- ルーターのアンテナが垂直になるように調整する(垂直方向が最適なルーターが多い)
- Wi-Fiを最も使用する場所からなるべく近い位置に設置する
- 壁や床の材質を考慮する(コンクリートや金属は電波を大きく減衰させる)
設置場所の効果を確認するには、スマートフォンの「Wi-Fi信号強度」を表示するアプリを使用すると便利です。家の各所で信号強度を測定すれば最適な場所を見つけることができます。
また、季節によって最適な設置場所が変わることもあります。夏と冬では家の温度分布が異なり、それが電波の伝わり方に影響することがあるため、定期的に見直すのも効果的です。
ルーター周辺の電波環境の最適化
ルーター自体の設置場所だけでなく、その周辺環境も重要です。特に夜間は日中と比べて使用する電子機器が変わることがあります。
ルーター周辺の電波環境を最適化するためのチェックポイントを以下にまとめます。
- スマートスピーカーやスマートホーム機器など、Bluetooth接続デバイスはルーターから離して配置する
- コードレス電話機やベビーモニターなど、2.4GHz帯を使用する機器との距離を確保する
- テレビやモニターなどの大型電子機器とルーターとの間に十分な距離を確保する
- 電子レンジの使用時は一時的にWi-Fi接続が不安定になる可能性を認識しておく
これらの基本対策を実施することで、多くの場合、夜間のWi-Fi接続問題は大幅に改善します。しかし、これらの対策を試しても問題が解決しない場合はより高度な解決策を検討する必要があるかもしれません。ここからはその方法を説明していきます。
Wi-Fiが繋がらない場合のより高度な解決策
基本的な対策を試しても夜間のWi-Fi接続問題が解決しない場合は、より高度な解決策を検討する必要があります。ここでは、ネットワーク環境を根本から改善するための方法をご紹介します。
メッシュWi-Fiシステムの導入
従来の単体ルーターでは対応しきれない広い家や電波の届きにくい間取りの場合、メッシュWi-Fiシステムの導入が効果的です。
メッシュWi-Fiとは、複数のアクセスポイントを連携させて家全体をカバーするシステムで、夜間の混雑時にも安定した接続を実現できます。
| メッシュWi-Fiシステム | 特徴 | 価格帯(2025年現在) |
|---|---|---|
| Google Nest Wifi Pro | Wi-Fi 6E対応、スマートホーム連携 | 2台セット 約40,000円〜 |
| Amazon eero Pro 6E | トライバンド対応、設定簡単 | 2台セット 約60,000円〜 |
| TP-Link Deco XE75 | コストパフォーマンス良好 | 2台セット 約40,000円〜 |
メッシュWi-Fiの設置ポイントは以下のとおりです。
- 設置場所は各アクセスポイント間が壁1枚程度の距離に収まるようにする
- 親機は必ずインターネット回線に直接接続する
- 子機は電波が弱い場所や利用頻度の高いエリアに設置する
ITmediaによるメッシュWi-Fi比較レビューによれば、夜間の混雑時でも単体ルーターと比較して20-40%の速度向上が見られたというデータがあります。メッシュWi-Fiを導入する際は最新のWi-Fi 6/6E対応モデルを選ぶと将来性が高く、コストパフォーマンス的にもおすすめです。
Wi-Fi中継器の活用
メッシュWi-Fiの導入が難しい場合は、Wi-Fi中継器(エクステンダー)の活用も効果的です。中継器は既存のWi-Fi信号を受信して再送信することで、電波の届く範囲を拡大します。
中継器選びのポイントは以下のとおりです。
- 既存のルーターと同じメーカーの製品を選ぶと互換性が高い
- デュアルバンド以上の製品を選ぶと通信速度の低下を抑えられる
中継器を設置する際の注意点は以下のとおりです。
- ルーターと中継器の間に大きな障害物がないこと
- 電子レンジやコードレス電話など、電波干渉源から離すこと
- 壁や家具の影響を受けにくい高さに設置すること
設置場所は既存ルーターの電波が十分届く場所で、かつ電波の弱いエリアに近い位置が最適です。
有線LANの併用
安定した接続を確保するために最も確実な方法は、有線LANで接続することです。
有線LAN活用のメリットを以下にまとめます。
- Wi-Fiよりも安定した接続速度を確保できる
- 夜間の混雑に影響されない
- 接続の遅延が少ない
- セキュリティ面でもWi-Fiより安全
オンラインゲームやテレビ会議、大容量ファイルのダウンロードなど、安定した接続が必要な作業は有線LANを使用するのが賢明です。
回線プラン・速度の見直し
Wi-Fiの接続問題が慢性的に発生する場合、契約しているプランが実際の使用状況に適していない可能性があります。
見直す際のポイントを以下にまとめます。
- 契約速度と実測速度の乖離を確認する(夕方〜深夜の時間帯に複数回測定)
- 家庭内の同時接続デバイス数とその使用帯域を把握する
- 料金プランと速度のバランスを再評価する
回線速度の目安は以下のとおりです。
| 家庭内の利用状況 | 推奨最低速度 | 理想的な速度 |
|---|---|---|
| 標準的な利用(Web閲覧、SNS、動画視聴) | 50Mbps | 100Mbps |
| オンライン授業・テレワーク+家族の利用 | 100Mbps | 200Mbps以上 |
| 4K/8K動画、オンラインゲーム、複数デバイス | 200Mbps | 500Mbps以上 |
| スマートホームデバイス多数+上記すべて | 500Mbps | 1Gbps以上 |
2025年現在、多くの光回線事業者が提供するプランでは、理論上は1Gbpsや10Gbpsといった高速通信が可能です。しかし、総務省の速度測定ガイドラインによると、実際の速度は契約速度の50-70%程度になることが多いとされています。
特に夜間は多くのユーザーが同時に接続するため、以下の対策を検討することも重要です。
- IPv6(IPoE)接続に対応したプランへの変更
- 混雑の少ないプロバイダへの乗り換え
- 固定IPアドレスプランの検討(業務利用の場合)
みんなのネット回線速度のような実測値比較サイトを参考に、夜間の実効速度が高いプロバイダを選ぶことも効果的です。
これらの解決策を組み合わせることで、Wi-Fiの接続問題は大幅に改善できるでしょう。特に、複数のデバイスを同時に使用する家庭では、単一の対策だけでなくメッシュWi-Fiと有線LANの併用、適切な回線プランの選択など、複合的なアプローチが効果的です。
まとめ
Wi-Fiの接続トラブルは回線混雑や電波干渉の増加など、複合的な要因で発生します。基本対策として、ルーターの再起動やチャンネル最適化が効果的です。改善が見られない場合はメッシュWi-Fiシステム導入や中継器の活用を検討しましょう。夜間の接続問題は2025年も続く課題ですが、Wi-Fi 6対応機器への更新や各通信事業者の混雑対策サービスを利用することで、大幅な改善が期待できます。夜でも快適なWi-Fi環境を実現するには、機器と設定の両面からのアプローチが必要です。